

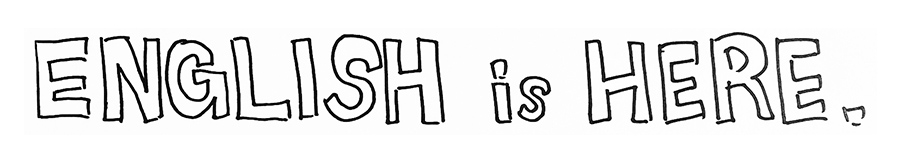
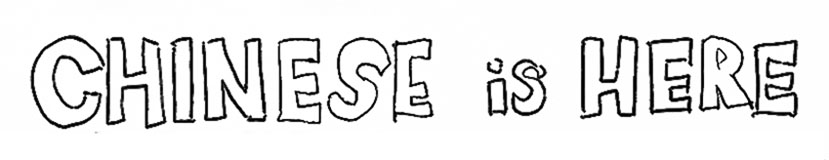
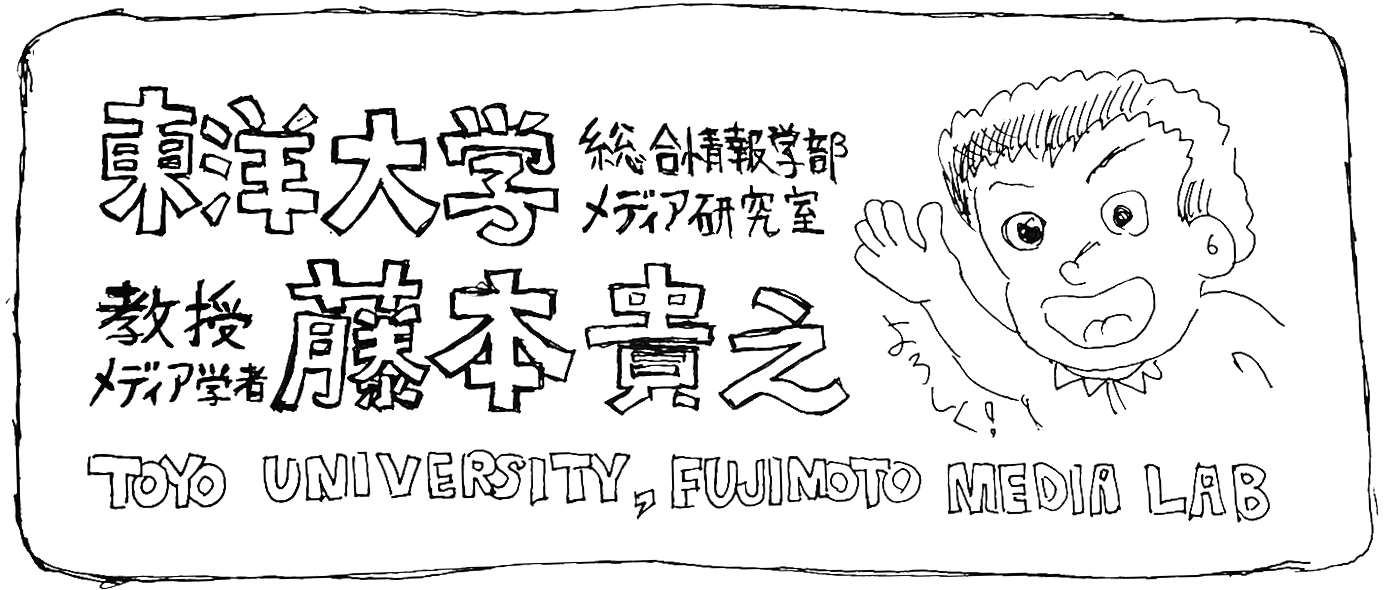


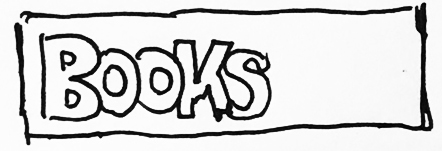


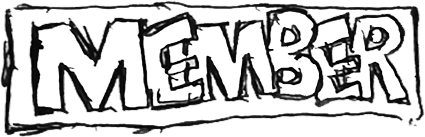






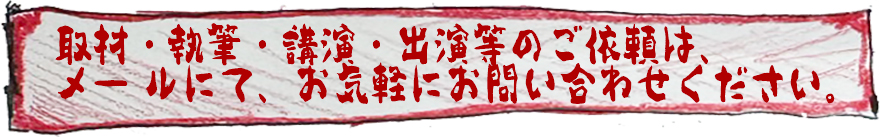

藤本研究室では、IT分野、メディア分野の専門家や研究者を目指す大学院生、留学生を募集しています。
私たちの研究室では、あらゆるジェンダー、宗教、人種、言語、思想を受け入れ、尊重します。藤本研究室では、誰もが自分のルーツやポリシーへの尊敬が保証された研究環境での自由な研究活動が実現できます。なお、研究・教育には日本語および英語を利用しますが、中国語によるサポートは可能です。

藤本研究室の研究活動|How about Fujimoto Lab.
東洋大学・藤本研究室では、主に以下に分野を柱に、世界を舞台にした研究活動を展開しています。
- 情報デザイン(Information Design)
- 人工知能(Artificial Intelligence)
- eXtended Intelligence(拡張知能)
- メディア・デザイン(Media Design)
- メディアとAI(Media Studies and AI)
- 最先端映像制作(the most advanced Video and Image)
- アプリケーション開発(Application Development)
- 聖書メディア情報学(Bible Media Informatics)
- 応用情報学(Applied informatics)
- その他、メディア、デザイン、ITに関わるあらゆること!
藤本研究室は、全ての大学院生が世界で活躍できる研究を目指します。
博士課程、修士課程、留学生などが、お互いの様々な研究テーマについて議論し、理解を深め、幅広い知識と技術を身に付けます。藤本研究室での研究は、「日本語」と「英語」のどちらでも可能です。日本語が苦手な留学生は英語による研究や論文執筆でも卒業が可能です。また、日中バイリンガル、日英バイリンガルのスタッフが常駐していますので、中国語によるサポートも可能です。ただし、研究は中国語ではできませんので、ご注意ください。
藤本研究室のコンセプト|Concept of Fujimoto Lab.
『伝える技法・表現する技術』=伝達のデザイン
藤本研究室では、様々なデザインスキルを駆使することで、「伝えるための技法」、「表現するための技術」の向上を目指します。単に「内容が良い」というだけでは、伝えたいメッセージを効果的且つ的確にターゲットへと届けることはできません。プレゼンテーション技法から資料作成のテクニックまで、最先端且つ確実な「情報デザイン理論」に基づいて、「伝達のデザイン」を攻究します。
『メディア構造』=構造のデザイン
多様化・複合化・多次元化する今日のメディアにおいて、そのあり方を左右するのは、『コンテンツ』ではなく、むしろそれを下支える『構造』の側になる。メディアを構造の側からアプローチする様々な知見と技法を藤本研究室では開発・提案・提供しています。
『メディア・ブランディング』=価値形成のデザイン
藤本研究室では、多様化・多次元化する様々なメディアの中で、いかに効果的・機能的な自己のブランディング手法とその戦略について、最先端の知見を元に、研究・実践を試みます。これまで、企業・組織・個人・各種法人…と数多くのメディア・ブランディングを担当し、実践的な成果を上げてきました。
『多様化するメディアの意義と位置』=メディアのデザイン
メディアが多様化する中で、一見に便利/効果的な『進化』と思われる状況を体感している人も多いかもしれません。しかしながら、多様化・複合化するメディア機器やツール/システムの登場は、果たして私たちにとって、本当に『進化』なのだろうか?多様化するメディアの意義と位置を文化的・社会的・技術的・経済的な側面から分析し、その可能性と課題を浮き彫りにしてゆきます。
発展する人工知能(AI)と拡張する人間の知性=XI:eXtended Intelligence
XI(eXtended Intelligence<)は、今日のAI研究で発生している様々な課題や問題を解決するために、新しい了解として注目されているまったく新しい研究分野です。人間と競合したり、対立するコンピュータではなく、人間の創造性や可能性を「拡張」させるために、どのように知的コンピュータを利用するか、どのようなシステムを開発してゆくか、ということに焦点をあてます。XI研究において、主人公は常に「人間」です。藤本研究室で人間の知性の可能性と最先端メディアの知見を融合させます。
*外部資金獲得(2017〜)*
【科研費(2022〜2025)】

| 拡張知能(XI)概念に基づく「人間らしさ」を感じる人工人格の理論構築と実現
藤本(研究代表者)の研究課題「拡張知能(XI)概念に基づく「人間らしさ」を感じる人工人格の理論構築と実現」が日本学術振興会・科学研究費助成事業(科研費)に採択されました。研究期間は2022〜2025です。 |
【 三菱UFJ公益信託大畠記念宗教史学研究助成金(2020〜2021)】
 |
| 史的イエス・キリスト像に基づく「ヴィアドロローサ(苦難の道)」追体験アプリケーションの開発
藤本(研究代表者)の研究課題「史的イエス・キリスト像に基づく「ヴィアドロローサ(苦難の道)」追体験アプリケーションの開発」が三菱UFJ公益信託大畠記念宗教史学研究助成金に採択されました。研究期間は2020〜2021です。 |
【放送文化基金・研究助成(2018〜2019)】
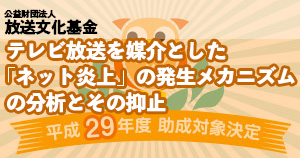
| テレビ放送を媒介とした「ネット炎上」の発生メカニズムの分析とその抑止
藤本(研究代表者)の研究課題「テレビ放送を媒介とした「ネット炎上」の発生メカニズムの分析とその抑止」が公益財団法人 放送文化基金の研究助成「平成29年度 【人文社会・文化】」に採択されました。研究期間は2018〜2019です。 |
【科研費(2017〜2020)】
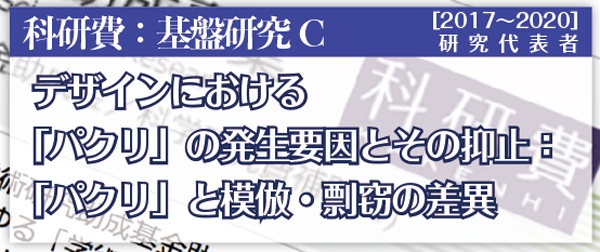
| デザインにおける「パクリ」の発生要因とその抑止:「パクリ」と模倣・剽窃の差異
藤本(研究代表者)の研究課題「デザインにおける「パクリ」の発生要因とその抑止:「パクリ」と模倣・剽窃の差異」が日本学術振興会・科学研究費助成事業(科研費)に採択されました。研究期間は2017〜2020です。 |
【KDDI財団・社会的・文化的諸活動助成(2010〜2011)】

| 産学連携・メディア教育プロジェクト・産学連携・東洋大学インターネット放送局事業
藤本(研究代表者)が公益財団法人KDDI財団の研究助成に採択されました。研究期間は2010〜2011です。 |

各種ご依頼・ご連絡・ご意見などお気軽にご連絡ください。基本的に1日以内にお返事いたしますので、もし、リアクションがない場合はメールが届いていない(あるいは見落とし)可能性がありますので、再度、ご連絡ください。
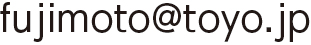
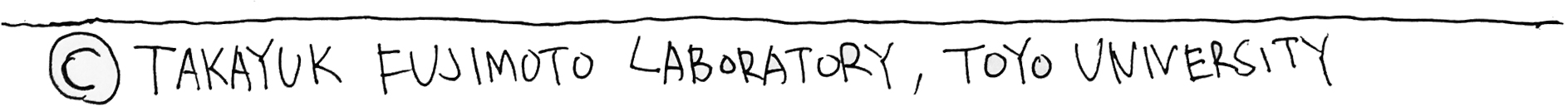
|
|